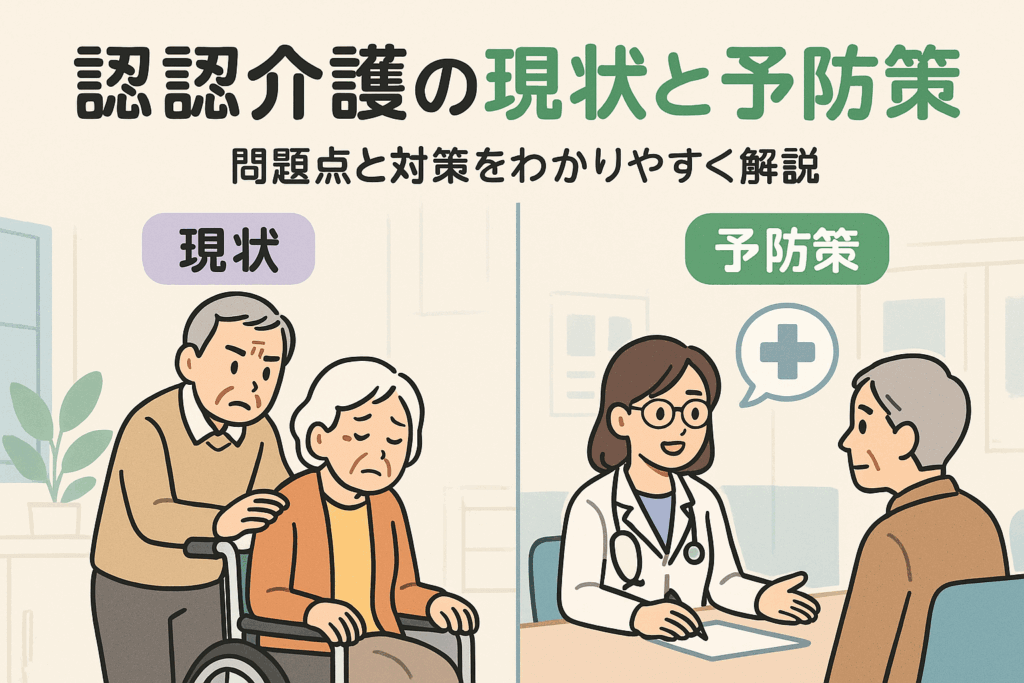「最近テレビや新聞で話題の“認認介護”という言葉、ご存じですか?いま日本では、認知症の高齢者同士で支え合う家庭が急速に増加しています。厚生労働省の調査によると、2022年時点で65歳以上の高齢者の約7人に1人が認知症を発症しており、認認介護世帯は年々増加傾向です。
『家族を支えたいけど、自分も介護が必要になったらどうしよう』『事故や金銭の管理が不安…』と悩む方も少なくありません。認認介護は、想像以上に多くのリスクや困難が潜んでいるのが現実です。
このページでは、認認介護の定義や老老介護との違い・具体的な問題と対策まで、最新のデータや現場の証言も交えて詳しく解説します。「今だけ」の知識ではなく、後悔しないために必要な情報を徹底的にわかりやすくまとめました。
あなたの大切な家族と自分自身を守るために、まずは正しい知識から始めてみませんか?続きを読めば、その第一歩がきっと見つかります。
認認介護とは何か?正確な意味と基本の読み方を理解する
認認介護の定義と基本概念の整理
認認介護とは、認知症の高齢者が同じく認知症の高齢者を介護する状態を指します。日本の高齢化が進む中で、最近とくに増加傾向にある社会課題です。要介護者も介護者も両方が認知症であるため、日常生活の中で多くのリスクや問題が生じやすいのが特徴です。
認認介護の現状としては、家族や配偶者同士で認知症を患うケースが増え、サポートを受けないまま生活する世帯も少なくありません。認知症の特性から、服薬ミスや火の不始末、徘徊など多岐にわたるトラブルが発生しやすい傾向があります。行政や専門機関による支援の重要性が叫ばれています。
表:認認介護の主なポイント
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 定義 | 認知症同士での介護 |
| 問題点 | 判断力・記憶力低下による事故や生活困難 |
| 増加背景 | 高齢化社会・晩婚化・子供世帯の独立 |
「認認介護の読み方」と関連語句の説明と使い分け
「認認介護」の読み方はにんにんかいごです。単語としては、「認(認知症)+認(認知症)+介護」と分かれます。同時によく使われる言葉には「老老介護(ろうろうかいご)」があります。老老介護は高齢者同士が介護を行う状況ですが、認認介護は特に認知症という点でより深刻な意味合いを持ちます。
関連語句で注意したい言葉:
-
認認介護(にんにんかいご):認知症の人が認知症の人を介護する
-
老老介護(ろうろうかいご):高齢者が高齢者を介護するが、認知症であるかどうかは問わない
認認介護という言葉はニュースや自治体の介護情報などでも頻繁に使用されています。
老老介護との違いをわかりやすく解説
認認介護と老老介護は似たような言葉ですが、背景やリスクが異なります。老老介護は介護者・被介護者の両方が高齢者であれば該当しますが、認知症かどうかは関係ありません。一方、認認介護は両者が認知症を発症しているため、より重篤な問題が起こりやすいのが特徴です。
下記の表で違いを整理します。
| 分類 | 主な対象 | 主なリスク |
|---|---|---|
| 老老介護 | 高齢者同士 | 体力・健康の低下による事故リスク |
| 認認介護 | 認知症同士 | 判断力低下による薬の管理ミス・徘徊・火事など重大事故 |
このように、認認介護は老老介護の中でも特異な課題を抱えており、外部からの支援や社会的な見守りの必要性が高まっています。
「認認介護とは簡単に」求めるユーザー向けのシンプル説明
認認介護とは、認知症の人が別の認知症の人の介護をしている状態のことです。介護する側もされる側も認知症のため、お互いに十分な判断が難しくなり、日常生活の様々な場面で問題が起こる可能性が高くなります。特に、緊急時の対応や日常の安全確保が難しく、家族や地域社会のサポートが不可欠です。認認介護は高齢社会の進展とともに増加しており、今後ますます注目される重要な社会課題となっています。
認認介護の現状と日本における社会的背景
最新統計データに見る認認介護の割合と推移
近年、日本では高齢化が進み、認知症の人が認知症の家族を介護する認認介護の問題が深刻化しています。厚生労働省による調査データでは、要介護認定を受けた高齢者のうち、およそ1割以上が認認介護の状況にあり、今後も増加が予測されています。特に高齢夫婦のみの世帯が増えた影響で、このような介護形態が顕著になっています。
下記のテーブルは、最新統計に基づく認認介護と老老介護の割合をまとめたものです。
| 介護形態 | 割合(推定) | 傾向 |
|---|---|---|
| 老老介護 | 約60% | 年々増加傾向 |
| 認認介護 | 約10~15% | 急増中 |
| その他 | 約25~30% | 比較的減少 |
このように、認認介護は老老介護全体の中でも無視できない割合に達しており、介護現場では増加する認知症介護の対応が急務となっています。
老老介護を含む高齢者介護全体における認認介護の位置づけ
高齢者介護世帯の多くは、親子や夫婦など家族内で支え合ってきましたが、主な担い手が高齢かつ認知症を発症している場合、介護の質や安全確保が大きな課題となっています。老老介護の中でも認認介護は、判断力低下や事故リスクの増加など特に深刻な問題を抱えています。
-
認知症症状による体調管理の困難
-
服薬ミスや金銭管理トラブルの危険
-
緊急時に適切な対応が難しい
このような実態を受け、地域や行政による支援体制の整備が求められています。
高齢化社会と家族構造の変化がもたらす影響
日本の高齢化率が上昇し続けるなか、家族の介護力は低下しています。かつては複数世代が同居する家庭が主流でしたが、現在は高齢夫婦のみ、単身高齢者を含む世帯が増加し、介護の担い手不足が顕著です。
-
1980年代は三世代同居が一般的
-
現在は単身・高齢夫婦のみの世帯が増加
-
介護者も高齢、認知症を患うケースが増えている
家族構造の変化により、在宅での介護負担が極端に高まり、認認介護の比率も上昇しています。
介護者人口の減少と介護難民問題との関連
介護する側も被介護者も高齢である場合、慢性的な人材不足が生じ、社会全体で「介護難民」の問題が拡大します。
-
介護を担う家族の数が減少
-
地域社会の支援や行政サービスへの需要増大
-
施設やケアマネジャー、訪問介護サービスの活用が重要
今後も高齢化が進む日本では、家族だけでなく社会全体で認知症介護に取り組む仕組みが不可欠です。支援センターや福祉サービスを適切に利用し、安全な生活の実現を目指すことが推奨されています。
認認介護で生じる具体的な問題点とリスクの詳細
食事・栄養管理の困難さによる健康リスク
認認介護の現場では、食事や栄養管理に深刻な問題が多数発生しています。認知症の症状が進行すると、食事の準備や適切な栄養バランスの維持が難しくなります。その結果、低栄養や脱水症状、食欲不振が増え、介護者・被介護者ともに健康を大きく損なう恐れがあります。
特に以下の問題がよくみられます。
-
食材や調味料の管理ができず、古いものを使ってしまう
-
食事回数や量が不規則になる
-
調理手順の誤りや火元の管理の問題
-
嚥下機能低下による誤嚥リスク増加
栄養不足は慢性疾患の悪化、免疫力の低下にもつながるため、周囲の支援と定期的な見守りが不可欠です。
薬の管理ミスや火の管理ミスに伴う事故危険
認知症同士の介護では、薬の飲み忘れや重複投与、さらには服薬時間の混乱がしばしば起こります。これにより重篤な副作用や症状悪化を招く恐れがあります。火の管理についても同様で、ガスの消し忘れやコンロの放置といったミスから火災事故が発生する事例も見受けられます。
下記に主なリスクをまとめます。
| リスク内容 | 具体例 |
|---|---|
| 薬の管理 | 薬の飲み忘れ、誤飲、重複服用 |
| 火の管理 | ガスコンロやストーブの消し忘れ |
| 家事全般 | 記憶障害・注意力低下による家電操作ミス |
薬や火の管理は深刻な生命リスクに直結するため、介護サービスや見守りセンサーなどの導入が推奨されます。
緊急時対応や金銭管理の課題
認認介護においては、日常生活のさまざまな管理が難しく、特に緊急対応が大きな課題です。急な体調悪化、転倒やケガが発生した場合、適切な連絡や救急要請が困難な場合があります。
また、金銭管理も問題となるケースが多いです。
-
公共料金や家賃の支払い忘れ
-
詐欺や不正請求への対応不能
-
現金の紛失や誤支出
金銭トラブルが生活の不安定化につながることもあります。支援センターや成年後見制度の活用、家族による定期チェックが重要です。
報告されている認認介護事件やニュース事例の分析
国内では認認介護に起因した痛ましい事件や社会的ニュースが報告されています。認知症同士による生活困難や事故、事故死、火災、失踪事件が発生し、大きな社会問題として認識されています。
最近のニュース例として
-
介護負担が限界を超えたことでの共倒れ
-
火の不始末やガス漏れによる住宅火災事故
-
行方不明や孤独死の発生
これらは周囲が介入できなかったための二次被害であり、早期発見・相談体制の強化が急務です。
事例から学ぶ対応の重要性と社会的課題
各事例は、日常的な確認不足や周囲の見守りの弱さが共通項です。社会全体で認認介護のリスクを共有し、地域ぐるみで見守る姿勢が必要です。在宅介護サービス、地域包括支援センターの積極活用、行政や医療機関との連携が今後の課題となります。
さらに、介護者・被介護者が安心して生活できる環境整備や、家族や地域コミュニティによる定期的なサポート体制こそが、多くのリスク低減に寄与します。
認認介護に至る複合的な原因と背景分析
経済的余裕のなさが招く認認介護の増加
経済的な余裕がないことは、認認介護が増加する大きな要因となっています。介護施設や専門サービスの利用には相応の費用がかかりますが、年金や貯蓄だけで介護費用を賄うのは難しい家庭が多いのが現実です。また、高齢夫婦だけの世帯などは収入源が限られ、経済的な制約から在宅での介護を選択せざるを得なくなります。
下記のテーブルは、経済的余裕が少ない世帯における認認介護発生率の傾向をまとめたものです。
| 状況 | 認認介護のリスク |
|---|---|
| 低所得・年金生活 | 非常に高い |
| 中所得 | 比較的高い |
| 高所得 | 低い |
生活費捻出の難しさが、必要なサポートの利用を妨げ、認認介護が結果的に増えてしまう現状があるのです。
頼れる家族や周囲の不足による孤立問題
家族や近隣の支援が得られない場合、孤立した環境で認認介護が発生しやすくなります。近年は核家族化や少子化の進行により、親や配偶者以外に頼れる人が減少。女性の社会進出や都市部への人口流出も、親族のサポートを受けにくくする一因です。
主な孤立要因を以下に示します。
-
子供が遠方で同居や支援が困難
-
地域との関わりが薄い
-
民生委員や支援センターへの相談機会が少ない
-
高齢者のみでの生活が長期化
このような孤立状態では、問題発覚や外部の介入が遅れやすく、介護リスクが高まります。
介護ストレスからの認知症発症リスクの相関
介護する側が強いストレスを受け続けると、自身も認知症を発症するリスクが高まることが知られています。睡眠不足や心身の疲労、社会的孤立が重なり、自覚がないまま症状が進行するケースも少なくありません。認知症の発症によって、介護の質や安全性が低下し、家庭内で事故やトラブルが発生することも報告されています。
具体的なリスク要因は以下の通りです。
-
長期にわたる介護による慢性的なストレス
-
休息や自分の時間の欠如
-
周囲からのサポート不足
このような悪循環が、認認介護世帯の問題を複雑化させる要因となっています。
老老介護との症状・リスク比較による違いの明確化
老老介護と認認介護は、いずれも高齢者同士の介護を指しますが、認認介護は介護する側も認知症であるため、危険性や複雑さがより深刻になります。特に認知症に起因する判断力や記憶力の低下が同時に起こるため、薬の管理ミスや火の不始末などの日常生活に起こるリスクが高くなります。
| 比較項目 | 老老介護 | 認認介護 |
|---|---|---|
| 介護する人 | 高齢者 | 認知症の高齢者 |
| 主要リスク | 体力低下等 | 判断力・記憶力の低下 |
| 発生しやすい事故 | 転倒・体調不良 | 火災・誤薬・事故 |
| 外部支援の要否 | 高い | さらに高い |
認認介護ではリスクの種類が増え、事故や事件の発生リスクも無視できません。早期発見と積極的な支援体制の重要性が強調されています。
現場の声と認認介護の実態を踏まえたケーススタディ
本人・家族・近隣の証言や体験談紹介
認認介護とは、認知症の高齢者が同じく認知症を患う家族の介護を担う状態を指します。現場から寄せられる声には、日常生活の中での多くの苦悩や困難が含まれています。
以下のテーブルは、実際に寄せられている主な証言や体験をまとめたものです。
| 証言者 | 主な内容 |
|---|---|
| 本人 | 家事の手順を忘れがちで、食事が作れなくなることがある |
| 家族 | 生活リズムの乱れや夜間の徘徊で見守りが増え、心身ともに疲労 |
| 近隣住民 | ゴミ出しの曜日や分別ができておらず、生活環境の悪化を感じる |
このような切実な証言から、認認介護に直面した世帯が日々感じている実態が見えてきます。特に家族内だけで問題を抱え込むケースが多く、外部からの発見やサポートが遅れることも指摘されています。
見過ごされがちなリスクと周囲の理解不足
認認介護は、目立たないまま問題が深刻化しやすい傾向があります。特に下記のようなリスクが指摘されています。
-
服薬や食事などの生活管理のミス
-
火災や転倒事故の増加
-
緊急時に適切な判断や対応が難しい
これらのリスクは認知症の症状による判断力や記憶力の低下が要因です。しかし認認介護の現状や課題については、まだ社会全体の認知度が十分とはいえません。正しい知識を持つことで、周囲が的確に状況を把握し、見守りや声掛けを行う土壌が必要です。
理解不足が続くことで、事件やトラブルが発生するケースもみられます。本人・家族ともに苦しみが積み重なり、近隣トラブルや孤立を深めることもあるため、早期のサポートが重要となります。
対応のための周囲の役割とサポート体制の必要性
認認介護への対策として、周囲や地域社会が果たすべき役割は大きいです。以下のアプローチが有効とされています。
-
地域包括支援センターへの相談
-
自治体や民生委員による定期的な見守り
-
ケアマネジャー、訪問介護サービスの積極的な利用
特に介護保険制度の活用や、地域コミュニティ全体での支援体制が不可欠です。定期的な訪問や地域住民とのつながりにより、異変を早期に察知しやすくなります。
また、近隣住民が生活の変化に気づいた際には自治体や支援センターに連絡することが推奨されます。こうしたネットワークがあることで、認認介護世帯が安心して暮らせる環境づくりが促進されます。
認認介護を未然に防ぐ予防策と迅速な解決方法
家族間での共有と事前計画の重要性
認認介護のリスクを減らすためには、家族間で情報や思いをきちんと共有し、具体的な計画を立てることが欠かせません。多くの家庭で最初は「まだ大丈夫」と考えがちですが、症状の進行や生活状況は突然変化することもあります。そのため、日常から定期的に話し合いを持ち、誰がどのような役割を担うか、いざという時の対応策を確認しましょう。
家族間のコミュニケーションでは、認知症の診断が下りた段階や介護の手間が増えてきたタイミングごとに以下の内容を話し合うのが理想的です。
-
現在の症状や介護の状態確認
-
家族ができるサポートや負担の分担
-
緊急時の連絡体制、かかりつけ医やサービス連絡先の確認
こうした事前準備がトラブルの予防に大いに役立ちます。
地域包括支援センター・専門家の役割と相談窓口情報
専門家のサポートを得ることで、早期発見と適切な支援に繋げやすくなります。地域包括支援センターは高齢者や家族の総合相談窓口として機能しており、認認介護のリスクや現状、具体的な解決策まで幅広くサポートしています。
全国の自治体には、以下の窓口や専門家が対応しています。
| 支援内容 | 相談先 |
|---|---|
| 介護保険・相談全般 | 地域包括支援センター |
| 介護サービス利用・申請 | 市区町村の福祉担当窓口 |
| 法的な不安・判断が難しい事例 | 社会福祉士・ケアマネジャー |
また、専門職による訪問や見守りサービスも活用すると安心です。困った時はなるべく早めに相談しましょう。
介護保険制度や成年後見人制度の効果的な活用法
介護保険制度は、在宅・施設・通所型サービスなど幅広い支援を受けるための基礎となっています。要介護認定を受け、高齢者自身と家族の負担を軽減できます。特に認知症の場合、介護プランの作成や施設利用において専門職が関与し、事故防止や生活環境の管理がしやすくなります。
成年後見人制度は、判断能力が低下した場合に財産管理や契約などを代行できる制度です。急な事件や支払い管理のミスを未然に防ぐ意味でも、早期の申立てや利用を検討しましょう。
-
要介護認定の申し込み
-
介護サービスの選択・組み合わせ
-
後見人制度の利用による財産・生活管理の強化
複数制度を組み合わせることで、より安心した日常を実現できます。
介護施設への入居やデイサービス利用の検討
家庭介護に限界を感じた時は、介護施設やデイサービスの利用も重要な選択肢です。認知症ケアに特化したグループホームや特別養護老人ホームでは、専門スタッフによる安全確保と生活支援が受けられます。
デイサービスの特徴
-
日中の活動・食事・見守り提供
-
介護者の負担軽減と休息確保
-
孤立や事故などのリスク低減
一方、施設入所も検討する場合は、情報収集や見学を早めに行い、家族の同意や本人の意向を尊重することが大切です。環境や費用、サービス内容など比較しながら最適な方法を模索しましょう。
認認介護や老老介護を巡る政策動向と今後の展望
政府・自治体の対応策や最新動向まとめ
日本では高齢化の進行によって老老介護や認認介護の割合が増加しており、政府や自治体が多方面で対策を進めています。厚生労働省は「地域包括ケアシステム」を推進し、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を送れるよう、医療・介護・生活支援を統合した政策を展開しています。
自治体では、認知症サポーター養成講座や認知症カフェの設置、見守りネットワークの構築が広がっています。支援センターやケアマネジャーによる個別支援の拡充、訪問看護・医療体制の強化も進行中です。
| 主な政策・支援 | 内容 |
|---|---|
| 地域包括ケアシステム | 医療・介護・生活支援を一体で提供 |
| 認知症サポーター養成 | 地域住民の正しい理解と見守り意識向上 |
| 相談窓口・支援センター | 高齢家族の相談およびサービス案内 |
| 見守り・緊急対応システム | 通報体制の整備や各種センサー利用など |
認認介護増加に対する社会全体の取り組み状況
認認介護が深刻化する中、地域や社会全体で支え合う仕組みづくりが重要視されています。家族だけで抱え込まないよう、地域ネットワークによる見守りやボランティア活動の参加が推進されています。企業やNPOも協力し、介護休暇制度の普及や、介護者支援セミナーの開催なども活発です。
社会では高齢者世帯が孤立しないよう、地域での声かけ運動や自治会の見回り活動が増えています。インターネットや電話を活用したオンライン相談やリモート見守りサービスも拡充しつつあり、多角的なアプローチが採用されています。
-
地域全体での見守り活動の強化
-
企業・NPOによる介護者向けセミナーや相談会の開催
-
オンライン支援などの新たな技術の導入
-
介護者同士の交流やサポートグループの設立
今後予想される介護ニーズの変化と対応の方向性
今後は、さらなる高齢化の進展に伴い認認介護や老老介護の事例が増加すると予想されます。認知症の高齢者が増えることで、介護の質や安全性へのニーズも多様化。より柔軟で専門的なサービスが求められるようになります。特に介護者の高齢化による負担軽減や共倒れ防止のため、外部サービスの利用が増加していくと見られています。
行政や地方自治体は、介護保険の拡充や次世代型支援サービスの開発を視野に入れています。デジタル技術を活用した見守り体制や、職員・ボランティアによる定期的な訪問支援の充実も計画されています。
| 今後への対応の方向性 | 主な内容 |
|---|---|
| デジタル見守りサービスの拡充 | センサー・オンライン通報などIT活用 |
| 専門職・多職種連携によるケアの高度化 | 医師、ケアマネジャー、看護師などが連携 |
| 介護者支援体制のさらなる強化 | 相談窓口・交流機会・介護休暇制度の拡充 |
| 予防・早期支援によるリスク軽減 | 地域啓発・サポートイベントの実施 |
多様化する課題に柔軟に対応するため、政策・地域・個人レベルでの持続的な連携と支援強化が今後ますます重要とされています。
認認介護に関する重要公的データと信頼性の高い資料まとめ
厚生労働省など公的機関の調査結果の紹介
認認介護の現状を正確に把握するため、厚生労働省をはじめとする公的機関による調査データが重要です。最新の国勢調査や高齢社会白書、認知症施策推進の報告書には、高齢者世帯や認知症を抱える家庭の実態、認認介護の割合などが収録されています。
下記のテーブルは主要な調査データの概要です。
| 調査機関 | 発表年 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 厚生労働省 | 2023年 | 老老介護・認認介護の世帯数推計と問題点 |
| 内閣府 | 2024年 | 認知症有病率、要介護人口の長期推計 |
| 総務省 | 2022年 | 高齢者世帯の生活状況と支援ニーズ |
これらの公的データにより、現状と課題を数字やファクトで把握できます。特に老老介護世帯が増加し、その中で認認介護の社会的影響が拡大していることが明らかになっています。
要介護認定者数や認知症患者数の推移データ
認知症の進行や高齢化によって要介護認定を受ける方が年々増加しています。特に認認介護世帯は、認知症患者が家族や配偶者を介護するため、支援体制構築が急務です。
下記は厚生労働省公開の主な推移データです。
| 年度 | 認知症患者数(推計) | 要介護認定者数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 約600万人 | 約690万人 |
| 2023年 | 約690万人 | 約749万人 |
近年、認知症に起因する介護事故や見守りの必要性が増しています。要介護度が高い世帯や共倒れリスクのある状況も懸念されています。今後も認認介護を抱える家庭が継続的に増加する見通しです。
介護保険事業計画に見る今後の展望と課題
介護保険制度は、認認介護を含む在宅介護の現状をふまえ、地域包括支援センターの機能強化や予防サービスの充実を目指しています。新たな基本介護保険事業計画では下記が盛り込まれています。
-
地域に密着したケアマネジャーや訪問看護師の配置拡充
-
介護予防・生活支援サービスの質向上
-
認知症サポーター養成や相談窓口の体制整備
これら施策は、認認介護世帯の負担軽減、生活の質向上、孤立防止などに直結します。公的支援を積極的に活用し、早期対応・地域全体での見守り意識が重要となります。家族だけに頼らず、公的サービスと専門職の支えを得ながら、安心した日常生活が送れる環境づくりが今後の課題です。
認認介護に関するよくある質問とわかりやすい回答
認認介護とはどういう意味ですか?
認認介護とは、認知症を発症した高齢者が、同じく認知症の高齢者を介護する状態を指します。たとえば夫婦や親子など、介護をする側もされる側も認知症と診断されているケースが該当します。認認介護の「読み方」は「にんにんかいご」で、日常生活の多くが不自由になる中で支援が行われるため、社会的にも注目されています。
この状況では判断力や行動力が双方で低下しており、従来の介護よりもさまざまな危険や課題が生じやすいです。
特に高齢化の加速や家族構成の変化が背景にあり、認認介護は今後ますます重要な社会問題といえます。
認認介護の問題点は何ですか?
認認介護には多くの問題点・リスクが存在します。主に以下のような点が挙げられます。
-
双方の認知機能低下によるリスク増
-
食事や服薬の誤り、火の不始末などによる事故
-
緊急時の対応が難しく、発見や通報の遅れが発生しやすい
-
社会的な孤立や生活管理の困難
特に周囲との交流が減りやすいため、外部のサポートや地域包括支援センター、介護保険サービスなどへの早期相談が負担軽減につながります。問題を放置すると重篤な事故や健康悪化、社会的な孤立の深刻化につながる可能性があるため注意が必要です。
認知症で要介護5になると余命はどのくらいですか?
要介護5は、認知症を含む疾患により生活全般で最大限の介助が必要な状態を示しています。平均寿命には個人差がありますが、厚生労働省の調査や実態に基づき、要介護5の方の平均余命はおおむね1~3年程度とされています。
ただし、年齢・基礎疾患・家族や医療、ケア体制等により大きく前後します。より良い生活環境や適切な医療、介護サービスの利用などで寿命や生活の質を維持しやすくなるため、早期の支援が大切です。
老老介護世帯のうち認認介護の割合はどのくらいですか?
認認介護の割合は年々増加傾向にあります。厚生労働省の調査をもとにした推計では、老老介護世帯全体のうち認認介護に該当する世帯は約10~15%ほどとされています。
| 世帯区分 | 割合の目安 |
|---|---|
| 老老介護 | 約60%以上 |
| 認認介護 | 老老介護の約10-15% |
高齢化に伴い、今後も割合は増加すると考えられています。要介護者・介護者双方が認知症という深刻な状況には、地域や社会が連携した対応が不可欠です。
老老介護と認認介護、子どもにできることは何ですか?
子どもや家族ができることはたくさんあります。以下の項目を参考にしてみてください。
-
家族間の定期的なコミュニケーションや見守りを意識する
-
地域包括支援センターや民生委員、ケアマネジャーなど専門職へ早めに相談
-
利用できる介護保険サービス、訪問介護やデイサービスの情報収集や積極的利用
-
栄養管理や生活管理に注意し、無理のないサポート体制づくり
-
金銭管理や法的手続きなど将来的な備えも検討
家族や子どもが孤立せず、地域や専門サービスとうまく連携できるよう心がけることが大切です。無理をせず、外部の支援や制度も積極的に利用して自身の暮らしも守りましょう。