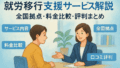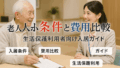「介護が必要になった家族のために、仕事をどう調整すればいいのか――」
そんな不安や悩みを抱えていませんか?実は近年、厚生労働省の統計によると【介護離職者は年間約10万人】にも達しており、将来を案じる方が増えています。
「介護休業制度」は、現役世代約5,700万人のうち、条件を満たせば誰でも最大93日まで取得できる公的制度です。正社員・契約社員・パートなど多様な働き方にも対応し、介護休業給付金という経済的な支援も活用可能。さらに【2025年4月の法改正】で対象範囲や取得要件が大きく変わり、より利用しやすくなりました。
「知らなかったばかりに費用もキャリアも失うところだった…」という後悔を未然に防ぐために、まずは最新の制度内容をしっかり知っておきましょう。
このページでは、「どんな家族が対象?申請手順は?給付金の金額は?」といった具体的な疑問を、公的データや実例をもとに、専門家監修でわかりやすく解説します。
最初から最後まで読むことで、あなたも”介護と仕事の両立”に一歩踏み出せる、リアルで信頼できる情報を得られます。
介護休業制度とは何か?制度の基本と目的をわかりやすく解説
介護休業制度は、家族の介護を必要とする従業員が、一定期間仕事を休める法的な仕組みです。主に労働者が配偶者や親、子などの家族を介護する場合、最長で通算93日間まで取得できます。この期間は分割取得も可能です。各企業は従業員の申請を拒否できず、制度の利用にあたっては従業員本人と介護対象者が要件を満たすかを事前に確認する必要があります。近年、「家族介護と就労の両立」に対する社会的な要望が高く、育児・介護休業法による保護が強化されています。
休業期間中に賃金が支払われない場合も多いため、雇用保険から「介護休業給付金」が支給されます。この制度によって、経済的な負担を大きく減らしつつ、安心して介護に専念できるのが特長です。申請条件や流れは厚生労働省のリーフレットでも詳しく案内されています。
主なポイントをまとめると、以下の通りです。
-
家族介護を理由に仕事を休める法的制度
-
対象は配偶者、親、子、孫、兄弟姉妹、配偶者の父母など
-
休業可能期間は原則として1家族につき93日
-
介護休業給付金で収入減少リスクを軽減
-
厚生労働省が定めた判断基準と手続きが必要
介護休業と介護休暇の違いを具体的に整理
介護休業と介護休暇は目的や利用できる日数、制度運用の仕方に明確な違いがあります。最大の違いは、「介護休業」が家族1人につき通算93日間までの長期休業であるのに対し、「介護休暇」は年間5日(家族が2人なら10日)までの短期的な休みを取得できる点です。さらに、介護休業は分割取得も可能ですが、介護休暇は時間単位取得もできるのが特徴です。
以下の表に両者の違いを整理します。
| 制度名 | 休業・休暇日数 | 特徴 | 給付金 | 対象 |
|---|---|---|---|---|
| 介護休業 | 最長93日(分割可) | 長期の家族介護に対応 | あり | 労働者 |
| 介護休暇 | 年5日または10日 | 短期・突発的な看護や通院等に対応 | なし | 労働者 |
介護休暇は主に急な通院や介護サービスの付き添い、書類申請など、日常生活をサポートする用途に重宝されます。一方、介護休業は認知症や重度障害による長期的な支援が必要な場合に活用されます。それぞれの利用場面を明確に意識して申請することが大切です。
2025年の育児・介護休業法改正ポイント
2025年の法改正により、育児・介護休業法はより柔軟で実用的な内容へ強化されます。主な変更点は下記の通りです。
-
取得要件の緩和:これまでは一定の雇用期間が条件でしたが、短期間勤務やパートタイム労働者にも利用しやすくなります
-
企業の義務強化:制度の説明や必要な環境整備を企業に義務付け、職場全体で介護と仕事の両立支援を促進します
-
柔軟な働き方への対応:テレワークやフレックスタイム制など、多様な勤務形態が選択しやすくなります
-
ハラスメント防止対策:介護休業取得に伴う不利益な取り扱いの禁止や相談体制の整備がより厳格に
これらにより、これまで利用しにくかった非正規やパートタイマーもより安心して制度の恩恵を受けられます。家庭状況ごとの多様な働き方が可能になり、介護による離職リスクも大きく低減できるようになります。今後はさらに制度内容を確認し、働くすべての方が安心して相談・申請できる環境が重要となります。
介護休業制度の対象者・対象家族・利用条件を詳細解説
介護休業制度は、仕事と家族の介護を両立したい方を支援するために設けられた法律上の制度です。この制度を利用することで、家族が要介護状態となった場合に一定期間の休業が可能となり、雇用や経済的な不安を大きく和らげることができます。休業期間中は条件を満たせば介護休業給付金を受け取ることもできます。「介護休業制度とは何か」「自分や自分の家族が対象になるのか」「どうやって利用できるのか」という疑問を持つ方が多いため、その詳細をわかりやすく解説します。
正社員、契約社員、パートタイム労働者の違いと取得要件
介護休業制度は正社員だけでなく、契約社員やパートタイム労働者にも適用されます。ポイントを下記のテーブルで整理しました。
| 雇用形態 | 取得要件 | 注意点 |
|---|---|---|
| 正社員 | 雇用期間・契約満了予定が1年以上あり、同一事業主に継続雇用されていること | 一般的に取得しやすい |
| 契約社員 | 雇用期間1年未満でも実質的に継続雇用見込みがあれば取得可能 | 雇用契約満了日と介護休業予定日が重なる場合は注意 |
| パートタイム | 週所定労働日数・時間の要件無し。条件を満たせば取得可 | 同上。契約更新が見込める場合は利用可能 |
-
取得には事業主への事前申出が必要です。
-
雇用形態による「利用不可」は原則なく、要件を満たせば広く認められます。
-
労働契約や就業規則の規定を個別に確認することも重要です。
必要な資料や手続きを整えることで、雇用形態に関係なく制度利用のハードルを下げられます。
対象家族の範囲と介護状態の判断基準
介護休業制度の対象となる家族の範囲は非常に広く、実親だけでなく配偶者や子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母も含まれます。下記リストをご覧ください。
-
配偶者(事実婚も含む)
-
父母、義父母
-
子、孫
-
祖父母
-
兄弟姉妹
「同居」や「扶養」の有無は問われません。また、介護が必要な状態は「常時介護を必要とする状態」であると厚生労働省が定めており、原則として要介護2以上の認定が目安となります。判断に迷った場合は、主治医の意見書やケアマネジャーの評価を参考にするのがおすすめです。
介護対象者が複数いる場合、各人ごとに介護休業の申請が可能です。ただし、同一対象者につき通算93日を限度とし、分割取得もできます。
このように、対象家族の範囲と介護状態の基準を事前に確認することで、申請時の混乱を防ぐことができます。
介護休業の期間・回数・取得方法の詳細とリセット制度
原則的な93日取得のルールと分割利用の仕組み
介護休業制度は、家族の介護が必要になった労働者が最大で通算93日まで仕事を休める制度です。93日は1回でまとめて取得する必要はなく、3回まで分割して活用できる仕組みになっています。これにより、介護の状況や家族の状態の変化に柔軟に対応できます。対象となる家族には、配偶者・父母・子だけでなく、孫や兄弟姉妹なども含まれます。
休業日数のカウントは原則として暦日単位で行い、平日・土日祝も含めて数えます。分割取得の際は1回目・2回目・3回目にそれぞれ異なる期間で申請でき、労働者や家族の事情に合わせた運用が可能です。下記のテーブルで概要を確認してください。
| 取得回数 | 最大取得日数 | 分割申請可能 | 申請方法 |
|---|---|---|---|
| 1回 | 93日 | 不可 | 連続した93日以内で休業を申請 |
| 2回 | 93日以内 | 可 | 必要に応じて分けて申請(合計93日) |
| 3回 | 93日以内 | 可 | 3回まで分割(合計93日以内) |
延長・再取得できる条件と制度の運用上のポイント
介護休業の延長や再取得には一定の条件があります。原則93日を超える介護休業の延長はできませんが、例えば異なる家族で新たに介護が必要になった場合や、要介護認定が追加で出た場合は再度利用できるケースが存在します。要件を満たした場合、複数の家族ごとに個別で介護休業を取得することも可能です。
また「リセット」と呼ばれている仕組みについても注意が必要です。たとえば一度すべての93日を使い切った後、同じ家族の介護状態が変わっても原則再度取得はできません。ただし新たな要介護認定や別の家族の介護が発生した場合は新たにカウントされます。
主な運用上のポイント
-
同時期に複数人の家族が介護状態となった場合、それぞれ93日ずつ取得可能
-
介護の必要性がなくなった場合、申請すれば休業を途中終了できる
-
パートや有期契約の労働者も一定条件を満たせば介護休業申請が可能
制度運用には、職場との調整や事前申請が重要です。申請から開始まで、法律上2週間以上の事前通知が求められます。利用を検討する際は、会社の就業規則や厚生労働省のリーフレットも確認し、正確な情報で制度を活用してください。
介護休業給付金の計算方法・申請書類完全ガイド
支給対象条件と給付金額の具体的計算式
介護休業給付金の支給対象となるのは、原則として雇用保険に加入している労働者で、家族の介護のために介護休業を取得した場合に限られます。対象家族の範囲には配偶者、親、子、祖父母、兄弟姉妹、孫などが含まれ、パートタイムや派遣社員も一定の条件を満たせば申請可能です。主な支給要件は以下の通りです。
-
介護休業開始日以前2年間に、通算して12カ月以上雇用保険に加入していること
-
介護休業期間中の就労日数・時間が所定の範囲内であること
-
給付金申請時に必要な手続きが適切に行われていること
給付金額の計算式は、休業開始前6カ月間の賃金日額×支給日数の67%が基本です。最大93日間分支給され、この期間内で分割取得が可能です。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 給付金支給率 | 賃金日額の67%(休業期間中の賃金支給が80%未満の場合) |
| 支給期間 | 最大93日(分割取得可) |
| 賃金日額の計算基準 | 休業開始前6カ月間の総賃金÷180日 |
申請方法と書類の記入ポイントを段階的に解説
介護休業給付金の申請手続きは、制度を正しく活用するためにも重要です。手続きは勤務先を通じて行うことが基本であり、本人が直接ハローワークに申請する場合もあります。主な流れを分かりやすくまとめます。
- 勤務先へ介護休業の希望を申し出る
- 就業規則等を確認し休業取得
- 会社または本人がハローワークへ給付金の申請
- 必要書類を添付して申請
特に注意すべき申請書類は下記のとおりです。
| 書類名 | 記載のポイント |
|---|---|
| 介護休業給付金支給申請書 | 介護開始日、介護対象者との続柄、賃金の支払い状況を正確記載 |
| 介護対象家族の状況申立書 | 「常時介護を必要とする状態」の具体的根拠を明記 |
| 賃金台帳または給与明細の写し | 過去6カ月分で、賃金額と労働日数・時間が確認できる書類を用意 |
| 会社証明書 | 勤務実態や雇用契約条件などを正確に記載 |
申請内容が不十分だと給付金の支給が遅れるケースも多いので、事前に必要書類や記入方法をしっかり確認することが大切です。
申請失敗例と改善策、よくあるトラブル事例まとめ
介護休業給付金の申請に関するよくある失敗例を理解しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。代表的なケースと改善策を一覧で紹介します。
-
申請期限を過ぎてしまい給付金が受け取れなかった
- 速やかに会社と連携し、休業取得と同時に申請準備を始める
-
必要書類に不備があり再申請が必要になった
- 事前に提出書類リストや自治体・会社のフォーマットをよく確認
-
自己都合退職や就業日数オーバーで支給対象外になった
- 休業日数・就業条件をあらかじめ会社と共有し、疑問点は早めに相談
| トラブル事例 | 改善策 |
|---|---|
| 期限切れ申請 | 休業前の段階から申請スケジュールを作成し共有 |
| 書類記載不備 | 見本やガイド資料を事前にチェック |
| 給付金減額の誤認請求 | 会社やハローワークで事前に計算の確認を徹底 |
各種相談窓口や厚生労働省の公式パンフレットも活用し、不安や疑問は早めに専門機関へ相談することが安心して制度を利用するポイントです。
申請前の会社対応・就業規則の確認ポイントと実務フロー
会社が講じるべき措置と労使協定の重要点
介護休業制度の申請を受ける前に、会社はまず自社の就業規則や関連規定を詳細に確認することが求められます。特に育児・介護休業法への対応状況や、休業対象となる介護者の定義、必要な手続き書類など、運用に直結する基本条件を明確にしましょう。この確認は、今後のトラブル防止や従業員支援の質向上に直結します。
表:会社が確認・整備すべき主な項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 就業規則の整備 | 介護休業制度の記載有無、申請手続き・復職ルールの明文化 |
| 労使協定の締結 | 対象外とする業務(例:日雇い労働者等)の明確化、取得制限は法定範囲内での協定が必須 |
| 申請書類・フロー | 申請様式、提出期限、必要となる要介護状態の証明など |
| 社内周知・相談体制 | 制度内容のリーフレット配布やWeb掲載、相談窓口担当者の設置など |
労使協定を締結する際は、職場の実情や、従業員の状況に即した内容となっているかどうかがポイントです。特に正規・パート等の区分や、勤務日数による可否など、細かな条件設定が必要となります。
申請から休業、復職までの具体的手順フロー
介護休業の取得を円滑に進めるには、各ステップごとに的確な手続きを踏むことが重要です。以下に主な流れを整理します。
- 介護休業申請書を会社へ提出
- 必要に応じて要介護状態を証明する書類を添付
- 会社による就業規則・労使協定との照合、要件確認
- 会社から許可・開始日を正式通達
- 休業開始。期間は最大93日間を原則として3回まで分割取得も可能
- 介護休業給付金の申請(ハローワークでの手続きも発生)
- 休業中の連絡・必要な情報共有
- 休業期間満了後、所定の手続きで復職
休業中に業務連絡や会社からの書類請求がある場合は、素早く対応できるよう配慮が必要です。復職時には業務再開スケジュールや配慮事項を事前に共有し、スムーズな職場復帰を目指しましょう。
なお、申請から復職に至る流れに不安がある場合は、会社の人事労務担当や外部相談窓口に相談することが安心に繋がります。
仕事と介護を両立するための関連支援制度一覧と活用術
時短勤務やフレックスタイムなど多様な働き方支援制度の解説
介護休業制度のほかにも、仕事と介護を両立するための柔軟な働き方支援制度が多くの企業に導入されています。代表的なものとして、時短勤務制度やフレックスタイム制度、テレワークの導入があります。これらは労働者が家族の介護に必要な時間を確保しつつ、就業を継続しやすくするための仕組みです。特に時短勤務は介護を理由に1日の所定労働時間を短縮できる制度で、多くの企業で幅広い対象者に適用されています。フレックスタイム制を導入することで、労働者自身が始業や終業時間を調整でき、介護との調整がしやすくなります。これらの支援制度は介護離職防止にも効果的です。
| 制度名 | 内容 | 主なメリット |
|---|---|---|
| 時短勤務 | 所定労働時間を短縮して勤務が可能 | 介護へ割く時間が増える |
| フレックスタイム制 | 始業・終業時間を自由に設定 | 柔軟なスケジュール調整が可能 |
| テレワーク | 在宅やサテライトオフィス勤務が可能 | 通勤負担減・緊急時の対応がしやすい |
| 介護休暇 | 年間で一定日数の有給取得が認められる | 短期的な介護ニーズに迅速対応 |
企業が整備すべき介護支援制度と助成金活用のポイント
企業にとっても、介護と仕事の両立支援は重要な課題です。高齢化や介護人材不足が進む中、従業員の介護離職を防ぐために、介護休業や短時間勤務、テレワークの制度整備が求められています。企業が支援制度を導入することで職場の柔軟性が高まり、働きやすい環境が形成されます。また、厚生労働省では企業向けに各種助成金制度を用意しており、介護休業を取得しやすい体制を整えた場合や両立支援制度の導入時に利用可能です。これにより、企業側もコストを抑えつつ制度拡充が可能となります。制度導入と助成金の組み合わせにより、従業員満足度の向上や人材定着につながります。
| 支援制度 | 主な内容 | 利用できる助成金例 |
|---|---|---|
| 介護休業規程の導入 | 会社の就業規則等に介護休業に関する規程を設ける | 両立支援助成金(介護離職防止コース) |
| 両立支援窓口の設置 | 社内相談窓口や制度案内を明確にする | キャリアアップ補助金等 |
| 定期的な研修や周知 | 制度の内容や利用方法について従業員へ周知徹底 | 企業内研修助成金など |
ハラスメント防止と不利益取扱い禁止のための最新対応策
介護休業や時短勤務の取得時に、職場でのハラスメントや不利益な取扱いが発生しないよう配慮が必要です。法律上、介護を理由とした不利益取扱いは禁止されており、これには解雇や減給、評価の引き下げなどが含まれます。企業は従業員の権利保護と公正な待遇を徹底するため、管理職を対象としたハラスメント防止研修の実施や、相談体制の強化が求められます。万が一ハラスメントが疑われる場合は、社内相談窓口や外部機関に相談し、迅速な対応を心がけることが推奨されます。働く環境を守ることで従業員の安心感が高まり、介護休業制度の活用促進にもつながります。
| 不利益取扱い例 | 防止策として有効な企業対応 |
|---|---|
| 介護休業取得を理由に解雇 | 就業規則内で禁止事項として明記し周知徹底する |
| 賃金引き下げや評価低下 | 人事評価基準の明確化、取得前後の待遇差の排除 |
| ハラスメント・嫌がらせ | 専用相談窓口の設置や管理職向けハラスメント研修の実施 |
介護休業制度の実態データと利用者の声を踏まえた活用ガイド
制度利用率や業界別の取得実績データ公開
介護休業制度は、家族の介護を目的とした重要な労働法上の制度です。厚生労働省の最新調査によると、制度の認知度は約7割ですが、実際の取得率は全体で5%前後にとどまっています。業界ごとに見ると、公務・医療・金融などの大規模組織では取得実績が高い傾向があり、中小企業やサービス業では未導入・未活用が依然多い状況です。
以下のテーブルは、業界別の介護休業取得率や特徴をまとめたものです。
| 業界名 | 取得率(目安) | 特徴 |
|---|---|---|
| 公務・医療 | 約12% | 制度の周知・取得推奨、職場復帰支援も整備 |
| 金融 | 約9% | 福利厚生充実・手続きサポートあり |
| 製造業 | 約6% | 従業員数が多い分、柔軟運用も目立つ |
| サービス業 | 約2% | 非正規・パートに浸透しきれていない |
| 小売業 | 約3% | 人員が少なく取得に壁を感じる |
逆に非正規雇用・パートタイマーの取得率は非常に低く、知識不足や人手不足が活用の壁となっています。
利用者インタビューや事例紹介で現実的なメリットと課題を具体化
実際に介護休業制度を利用した方の声からは、現場でのさまざまなメリットと課題が分かります。
-
主なメリット
- 家族の介護に専念する時間が確保できた
- 国からの給付金で生活負担が軽減された
- 職場との調整がスムーズで安心して利用できた
-
主な課題や注意点
- 休業取得にあたり同僚の業務負担が増え、心理的に申し訳なさを感じた
- 会社によっては手続きや理解が進んでおらず、申請に苦労した
- 休業明けの配置転換やキャリアへの影響が心配との声も多い
特に休業を「使い切った」あとは延長が原則認められず、介護が長期に及ぶ場合の備えは重要です。現場の声を参考に、事前に相談窓口の利用や制度内容の理解を深めておくことが推奨されます。
介護休業と他の休暇・休業制度の使い分けポイント
介護休業のほかにも、介護と両立できる複数の制度があります。それぞれの特徴を理解し、状況に応じて最適な選択をすることが大切です。
| 制度名 | 目的・特徴 | 取得可能日数 | 支給・保障など |
|---|---|---|---|
| 介護休業 | 家族の常時介護が必要な時に長期で取得可能 | 最長93日×3回 | 介護休業給付金が原則支給 |
| 介護休暇 | 通院付添や一時的な介護時に短期取得 | 年5日(2人以上10日) | 無給の企業多い(有給も一部) |
| 短時間勤務 | 介護と仕事を両立させるため就業時間を短縮 | 制度利用中 | 賃金は勤務時間分按分 |
| 所定外労働制限 | 残業免除やフレックスタイム勤務の導入 | 制度利用中 | 労使協定等で条件設定が可能 |
複数の制度を併用することで、介護と仕事の両立が現実的になります。特に介護休業と介護休暇の違い(長期・短期)や給付金の有無はしっかり確認しましょう。会社の就業規則や相談窓口も活用することで、最適な制度利用が可能です。
介護休業制度に関するよくある質問(FAQ)に回答し疑問を解消
給付金の支給日や手続きのタイミングについて
介護休業給付金を受け取るには、休業開始後すみやかに企業を通じてハローワークに申請書類を提出する必要があります。申請から支給までの期間はおおむね1〜2ヶ月程度かかるのが一般的です。申請は1ヵ月ごとに行い、必要な書類は「介護休業給付金支給申請書」「事業主証明書」などです。支給日やタイミングを逃さないよう、事前に企業の人事やハローワークに相談し、正確なスケジュールを確認しましょう。支給金額は原則として休業前賃金の67%が上限です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請タイミング | 休業開始ごとに1ヶ月単位で申請 |
| 必要書類 | 申請書、事業主証明書など |
| 支給日数 | 申請後およそ1〜2ヶ月 |
| 金額 | 賃金の67%が上限 |
介護休業の最大取得可能日数と条件
介護休業は、対象の家族1人につき通算93日までを3回まで分割して取得可能です。取得条件は、「常時介護を必要とする家族」がいることが必須条件で、介護状態の判定には厚生労働省の基準が用いられます。93日を超えて取得することは原則できませんが、やむを得ない事情がある場合や法改正等により延長されるケースもあります。休日や有給休暇との組み合わせも柔軟に可能です。
| 対象者 | 配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫など |
| 取得可能日数| 93日(分割可) |
| 条件 | 常時介護を要する状態であること |
契約社員やパートタイマーの利用可否
介護休業制度は、正社員だけでなく、一定の条件を満たす契約社員やパートタイマーにも適用されます。主な条件は「雇用期間が1年以上あり、かつ子が満満でない場合(未就学児)」とされていましたが、改正により条件緩和されているため、短時間勤務者・派遣社員も対象となる場合があります。企業ごとに就業規則の内容が異なるため、自身の雇用形態と制度の対象可否を就業前に確認しておきましょう。
利用が可能な雇用形態の例
-
正社員
-
契約社員(契約更新の可能性あり)
-
パートタイム労働者
-
派遣社員(派遣元での取扱いによる)
介護休業後の職場復帰や退職の扱い
介護休業後の職場復帰は、原則として元の職務または同等職へ復帰する権利が法律で守られています。ただし、復帰後に本人の事情や会社の事情により退職を選択するケースもあります。退職を希望した場合、介護休業の期間は社会保険や雇用保険に引き続き加入可能です。職場復帰が困難な場合、自己都合退職となりますが、介護離職による失業手当の特例も設けられています。復帰・退職を不安視する場合は、早めに専門家や労務担当に相談すると安心です。
介護休業と有給休暇、社会保険料の関係
介護休業を取得した期間は、有給休暇の消化とはみなされません。介護休業は無給となる場合が多いですが、一定の条件下で休業中の社会保険料が免除されます。免除対象となるのは、休業期間中に全く給与が支払われない場合などです。有給休暇と組み合わせて利用することも可能なので、計画的に活用することで家計への影響を抑えることができます。詳細は、企業の人事担当や社会保険事務所に事前確認するとよいでしょう。
ポイント
-
介護休業=有給休暇とは別枠
-
社会保険料の免除制度を活用できる場合あり
-
有給休暇との併用で所得の減少を部分的に補填可能