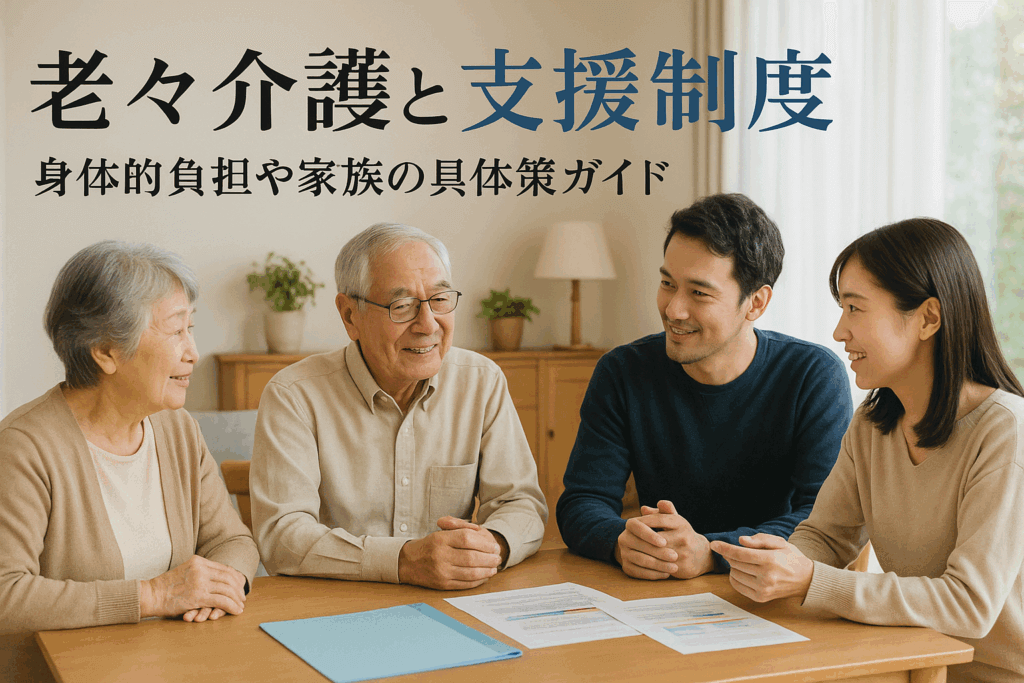高齢化が進む日本では、65歳以上の方が介護の担い手・受け手となる「老々介護」が身近な課題となっています。厚生労働省の調査によると、実際に65歳以上が主たる介護者となっている世帯は【約65%】にものぼり、ここ10年でその割合はさらに上昇傾向です。
「自分も同じような状況になるのでは…」「毎日どこまで頑張ればいいの?」と不安を感じていませんか?特に家族のみで介護を続けるケースでは、身体だけでなく心の疲労や経済的な問題が深刻化しやすい現状が報告されています。
中には、介護者も高齢であるために双方の健康リスクが高まり、“共倒れ”が現実になるケースも。介護関連費用も月平均約【7万8000円】と、長期化すれば家計への負担がじわじわと重くなる実態があります。
この記事では、最新の統計や社会背景をもとに老々介護の基本から、よく直面する悩みや支援策まで網羅的に解説。最後まで読むと具体的な対策や頼れるサービスの活用法がしっかり分かり、迷いを一歩前進させるヒントが見つかります。
今こそ、知識と備えで「もしも」に向き合いませんか?
老々介護とは何か?基本の理解と社会的背景
老々介護の定義と歴史的変遷
老々介護とは、高齢者が配偶者や兄弟姉妹など、同じく高齢の家族や親族を介護する状況を指します。平均寿命の延伸や核家族化の進行を背景に、身内の高齢化が介護現場にも大きな影響を及ぼしています。このような介護の形態は日本独自の課題と思われがちですが、現在は海外でも注目されており、高齢化社会に共通する悩みといえます。
老々介護の呼称と英語表記の解説
老々介護の読み方は「ろうろうかいご」で、英語では「Elderly Care by the Elderly」や「Elder-to-Elder Care」と表記されます。同様の言葉に「認認介護(にんにんかいご)」がありますが、これは認知症の高齢者同士による介護を指す言葉です。日本独自の言葉であり、国際的にもそのまま使われることが増えています。
老々介護の現状と統計データ
近年、老々介護の世帯は増加傾向にあります。厚生労働省の調査によると、在宅介護を行う主な介護者のうち、65歳以上が占める割合は約7割に達しています。これは親子二世代以上が同居する家庭が減少し、高齢の夫婦のみの世帯が増えていることが主な要因です。
介護者・被介護者の平均年齢を比較すると、被介護者は80代後半、介護者も70代~80代前半が中心となっています。
介護者・被介護者の年齢別割合と最新推移
下記の表は、介護者と被介護者の年齢構成の一例です。
| 年齢層 | 介護者割合 | 被介護者割合 |
|---|---|---|
| 60~69歳 | 15% | 7% |
| 70~79歳 | 40% | 23% |
| 80歳以上 | 45% | 70% |
年を追うごとに、介護者・被介護者ともに高齢化が進行しています。
老々介護が増加した社会・人口動態上の背景
老々介護が増加した要因として、まず挙げられるのが少子高齢化と核家族化です。これにより、子供と同居せず高齢者夫婦が二人だけで暮らす世帯が増えています。さらに平均寿命が男女ともに延びた結果、自宅で高齢者が高齢配偶者の介護を担うケースが多くなっています。
また、下記のような背景も大きく影響しています。
-
家族構成の変化による支援者の減少
-
女性の社会進出により、子世代が介護を担いにくくなった
-
介護サービスへのアクセス格差
このような社会的環境の変化が老々介護の増加に拍車をかけていることは明らかです。今後は適切な支援制度や地域ネットワークの活用が、ますます重要になると考えられます。
老々介護が直面する主な課題と問題点の詳細分析
身体的・精神的負担の実態と共倒れリスク
高齢者による介護、いわゆる老々介護は年々増加しており、総務省や厚生労働省の調査によれば、その割合は世帯全体の約6割にも上ります。身体的負担は、加齢に伴う体力低下や持病により、些細な動作でも介護疲労を招きやすくなります。精神的負担も見過ごせず、長期間にわたる介護で孤立感やストレスを感じやすい状況です。とくに、認知症の症状が進行している場合は、見守りや対応が困難となり、2人同時に健康を損なう「共倒れ」のリスクが高まります。
介護現場でよくみられる負担の例
-
睡眠不足
-
体重減少や体調不良
-
社会とのつながりの希薄化
このような状況に陥ると、支援サービスの利用や相談窓口での情報収集が重要となります。
経済的負担と介護費用の壁
老々介護では、介護に必要な費用や生活費の工面が大きな課題となります。介護保険制度を活用できるものの、全ての介護費用をカバーできるわけではありません。また、年金収入だけでは十分でない世帯も多く、追加費用や介護用品、福祉用具の購入、在宅改修など様々な支出が重なります。
下記の表は、老々介護にかかる主な費用の一例です。
| 費目 | 月額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 介護サービス | 20,000円〜 | サービス内容で変動 |
| 介護用品 | 5,000円〜 | 紙おむつ、消耗品 |
| 住宅改修費 | 一時費用数十万円 | 手すり設置など |
| 医療費 | 10,000円〜 | 持病がある場合 |
経済的な負担を軽減するには、市区町村の助成制度や介護保険外の支援策の情報収集が不可欠です。
社会的孤立と支援不足の問題
介護のほとんどが自宅で行われるため、高齢の介護者は外部との接触が減り、社会的孤立に陥りやすい傾向があります。周囲に頼れる親族や知人がいないケースも珍しくなく、悩みを相談できないことから心理的ストレスが増大します。こうした孤立を防ぐには、地域包括支援センターや訪問型サービスの積極的な利用がカギとなります。
社会的孤立を防ぐための取り組み例
-
地域サロンや交流会への参加
-
介護者向け相談ホットラインの活用
-
ボランティアによる訪問サービス
専門機関のサポートを積極的に取り入れることで、心身両面の負担軽減につながります。
老々介護急増の背景を人口・社会構造の視点から深掘り
超高齢社会の到来と団塊世代の役割
日本は世界に類を見ない速さで高齢化が進んでいます。65歳以上の人口割合は年々上昇し、2025年には全人口の約3割に到達する見通しです。その中心には、団塊世代の高齢化という大きな社会変化が関わっています。特に「老々介護」とは、主に高齢者同士、特に夫婦間や兄弟姉妹間で介護を担う状況を指します。最新の調査では、介護が必要な人を65歳以上の配偶者が介護している割合が全体の5割以上を占め、今後もこの傾向は続くことが予想されています。
下記の表は、老々介護世帯の増加傾向を示しています。
| 年 | 65歳以上が主介護者の割合 |
|---|---|
| 2000 | 31% |
| 2010 | 44% |
| 2020 | 53% |
高齢者世帯が増加し家族構成も変化するなか、今後もさらなる問題の拡大が懸念されています。
健康寿命と平均寿命の乖離問題
日本では平均寿命と健康寿命の差が課題となっています。平均寿命とは生まれてから亡くなるまでの年数、健康寿命は介護を受けず日常生活を自立して送れる期間を指します。この両者の差は男女とも約10年あり、高齢者は「長生き=元気」ではなく「長生き=介護が必要」の状態が増えがちです。
ポイント
-
男性:平均寿命約82年、健康寿命約72年
-
女性:平均寿命約88年、健康寿命約75年
この10年近いギャップが、「老々介護」状態を長引かせる主要な要因です。高齢者が高齢者を介護し続けることで、心身への負担や共倒れリスクが高まります。
介護保険制度の現状と制度面の課題
介護保険制度は2000年に創設され、高齢者の介護負担の軽減と自立支援を目的としています。制度の基本的な仕組みは次の通りです。
| 対象 | 内容 |
|---|---|
| 40歳以上 | 保険料納付が義務付けられる |
| 65歳以上 | 介護サービスの利用が可能 |
しかし、現場では制度の運用に課題が残ります。たとえば、認定を受けても必要なサービスが十分に行き渡らないケースや、支援が在宅中心となることで家族の負担がかえって増す場合も少なくありません。さらに、「認認介護」と呼ばれる介護者・被介護者とも認知症の世帯が増加し、専門的なサポートの必要性が高まっています。
介護保険に加えて地域包括支援センターなどの公的機関も活躍していますが、現実には利用方法や情報へのアクセスが難しいとの声も多く、早めの相談や情報収集が重要です。
老々介護を支える各種介護支援制度とサービスの実践活用法
公的介護保険制度の利用方法と申請プロセス
公的介護保険制度は、老々介護世帯を支える中心的な仕組みです。40歳以上の方が保険料を納付し、要介護認定を受けることで介護サービスが利用可能となります。申請の流れは次の通りです。
- 市区町村の窓口や地域包括支援センターに要介護認定を申請
- 認定調査員による自宅訪問と必要書類の提出
- 審査後、要支援・要介護度が決定
- ケアマネジャーがケアプランを作成し、必要なサービスを選定
要介護認定は高齢の世帯では身体的・心理的負担を軽減する重要な一歩となります。利用できるサービスの範囲や費用負担割合も知っておくと安心です。
地域包括支援センター・自治体窓口の活用
地域包括支援センターや自治体窓口は、老々介護の不安や課題を相談できる身近なサポート拠点です。介護保険申請や各種サービス利用、認知症・認認介護に関する専門的な情報提供を受けられます。
地域包括支援センターでできること
| サービス内容 | 詳細 |
|---|---|
| 介護・福祉相談 | 介護サービスの説明、利用方法案内 |
| 家族のサポート | 介護者への心理的、身体的負担軽減策の助言 |
| 認知症支援 | 専門スタッフが認知症ケアや症状管理の相談対応 |
| 地域との連携 | 医療・看護・福祉との情報共有や連携手続き支援 |
複雑になりがちな制度利用や課題への解決策も、専門スタッフによるアドバイスでスムーズに進めやすくなります。
多様な在宅介護サービスの種類と特徴
老々介護の現場では、各家庭に合った在宅介護サービスを賢く選ぶことがポイントとなります。利用できる主なサービスは以下の通りです。
-
訪問介護:ホームヘルパーが食事・入浴・トイレ介助を担当。認知症や身体機能低下にも対応できます。
-
デイサービス:日帰りでの入浴や機能訓練、レクリエーションを提供し、介護者の負担軽減にも有効です。
-
短期入所(ショートステイ):事情により一時的に施設で介護を受けたい場合に利用可能です。
-
訪問看護:医療的ケアや健康管理を看護師が支援します。
-
福祉用具の貸与・住宅改修:手すり設置や段差解消など、生活環境の整備も重要ポイントです。
それぞれのサービス特性や費用、利用方法を比較し、必要に応じて組み合わせることで、共倒れや介護疲れを予防できます。
民間介護サービスや見守りシステムの選び方
民間が提供する介護サービスや見守りシステムも、老々介護の負担を分散するうえで有効です。主な選択ポイントは以下の通りです。
-
見守りサービス:センサーやカメラで日常生活を遠隔からサポート。
-
配食サービス:バランスのとれた食事を自宅に届けることで食事面の負担を軽減。
-
家事代行サービス:掃除・洗濯・買い物など、日常生活のサポートを受けられます。
-
緊急通報システム:急な体調不良や転倒時にも迅速な対応が可能。
民間サービスの選定時は、契約内容や費用、サポート体制を必ず確認し、高齢世帯の実情に合ったサービスを選ぶことが大切です。信頼性や地域での評判も選ぶ際の大きな指標となります。
老々介護の現場でよくある事例と対処の実践知識
老々介護は、高齢者が配偶者や同居する家族など同じく高齢者を介護する状況を指し、日本における介護世帯の割合も年々増加しています。下記のような場面で課題が生じやすく、適切な知識と対策が重要です。
生活の中で起こる典型的な課題と心理的葛藤
加齢とともに身体機能が低下する中、介護者も介護を受ける側も日々の生活でさまざまな困難に直面します。
-
心身の疲労やストレスの蓄積
-
認知症などによる意思疎通の困難
-
資金面や制度利用の経済的な不安
-
孤立感や支援の届かないもどかしさ
特に認認介護の場合、双方が認知症であることから安全管理が難しくなり、薬の管理や食事の失敗、夜間の徘徊なども課題です。心理的には「頑張らなければ」という使命感と、想定外のトラブル対応が負担の一因となっています。
介護者夫婦や認認介護の具体状況
| 状況 | 具体例 | 主な対応策 |
|---|---|---|
| 高齢の夫婦介護 | 夫が妻を介護、双方とも体力低下 | サポートサービスの利用、家事外注 |
| 認認介護 | どちらも認知症 | 見守り機器導入、多職種による定期的な見守り |
| 単身世帯援助 | 離れた家族が定期訪問 | 地域包括センターの活用、専門職の相談 |
トラブルや不和が起きやすい場面の具体事例
老々介護の現場では、ちょっとした行き違いが大きな不和に発展しがちです。よく発生するのは以下のようなケースです。
-
服薬ミスによる健康リスク
認知症の進行や意思疎通の齟齬から薬の過不足が発生しやすい
-
家計や費用のトラブル
介護費用の負担感や、金銭管理でのトラブル
-
日常生活上の衝突
入浴・排泄・食事補助を巡る役割分担の不満や疲労
-
家族間・きょうだい間の意見対立
離れて暮らす子供や親戚と介護方針で揉めることも多い
強調したいポイントは、こうしたトラブルは避けられないものとして捉え、早めの相談や外部支援の導入を検討することです。
先進的な解決アプローチと成功事例の紹介
近年は介護者の負担を減らし、共倒れや孤立を防ぐための多彩な支援策やテクノロジーも登場しています。
-
地域包括支援センターによる継続的フォロー
-
訪問介護やデイサービスの併用
-
介護保険サービスでの費用軽減
-
民間見守りサービスや遠隔安否確認システムの活用
-
専門家のチームによる個別ケースカンファレンス
成功事例として、地元ケアマネジャーと連携し、週3回の訪問介護を導入したケースでは、介護者のストレスが大きく軽減。さらに住環境をバリアフリー化し、転倒事故が予防されたという声もあります。
効果的な対策を講じることで、より安心で持続的な介護環境が実現できます。「困った時はひとりで抱え込まず、社会資源や外部サービスを積極的に使う」ことが、今後の老々介護の最善策となっています。
老々介護における家族(子供・孫)による現実的なサポート法と心構え
老々介護における家族の役割と期待される支援
老々介護とは、高齢者同士が介護を担う状況を指します。近年、長寿化が進み、老老介護や認認介護の割合が増加しています。家族、特に子供や孫によるサポートは、心身の負担を軽減し、共倒れを防ぐうえで重要です。下記の表にて家族ができる具体的支援方法を整理しています。
| 対応策 | 内容 | 効果 |
|---|---|---|
| 定期的な訪問 | 日常の見守りや会話を心がける | 孤独感緩和・異変の早期発見 |
| サービス利用 | 介護保険、訪問介護、デイサービス等 | 介護負担分散・介護者の休息確保 |
| 生活環境改善 | バリアフリー化や転倒防止 | 事故リスク低減・安全な生活の実現 |
家族としてできる範囲での見守りや、施設・サービスの積極活用が求められます。その際、無理に一人で抱え込まない意識も大切です。
家族間コミュニケーションの改善策
老々介護に直面する家庭では、家族間の連携が大きな支えとなります。兄弟姉妹や親族と定期的に情報共有し、役割分担や協力体制を明確にしておくことがポイントです。
-
家族会議の定期開催…介護方針や現状報告を話し合い、全員が状況を理解します。
-
負担の偏りを防ぐ…一人に責任が集中しないよう、役割を分散させます。
-
予防的行動の共有…転倒や疾患への注意点など、予防策の情報を家族間で共有しましょう。
話し合いや情報共有を通じて、意見の食い違いを減らし、介護者の孤立やストレスを防ぐことにつながります。
精神的負担軽減のための支援と相談窓口案内
介護は精神的な負担も大きくなりがちです。悩みを一人で抱えず、支援制度を活用することが重要です。以下のような相談先が利用できます。
| 窓口・サービス | 主な相談内容 |
|---|---|
| 地域包括支援センター | 介護制度・サービス紹介 |
| 市区町村の福祉課 | 経済的支援・介護保険申請等 |
| 民間の電話相談窓口 | 精神的サポート・悩み相談 |
このほか、認知症の場合は専門医やかかりつけ医にも相談可能です。定期的な利用者支援やカウンセリング、ヘルパー派遣など、複数の制度や支援サービスを併用しながら、無理なく介護に向き合う姿勢が大切です。家族全員で支え合うことで、負担を減らし、より良い介護環境を築きましょう。
老々介護の予防と健康寿命を伸ばす生活改善策
日常生活で取り入れられる健康管理法
老々介護を予防し健康寿命を伸ばすには、日々の生活習慣を見直すことが大切です。特に、高齢者の体力維持と認知症の予防には、バランスの良い食事や適度な運動が不可欠です。朝・昼・夜と3食を決まった時間に摂り、塩分・糖分の摂取を控えるようにしましょう。週に2〜3回のウォーキングや室内体操を日課にすることで、転倒リスクの軽減や筋力低下の予防につながります。さらに、脳トレや趣味活動を続けることで認知機能の低下を防ぐことができます。
| 健康管理ポイント | 内容 |
|---|---|
| 食習慣 | 野菜・魚・たんぱく質を中心に、規則正しく3食食べる |
| 運動習慣 | 毎日30分程度の散歩や体操 |
| 睡眠 | 7時間以上の質の高い睡眠を意識する |
| 交流 | 家族や友人との会話、地域活動に参加 |
生活を見直すことで心身ともに健康を維持しやすくなり、将来的な老々介護のリスクも減らせます。
地域介護教室やサポートグループの効果的利用
地域で提供されている介護教室やサポートグループを活用することで、家族だけで抱え込む状況を防ぎやすくなります。介護教室では、正しい介護技術や認知症への接し方、感染症予防や食事ケアなどの知識が身につきます。また、サポートグループでは同じ悩みを持つ方と交流ができ、心理的な負担を軽減できるのも大きなメリットです。
効果的な地域サポートサービス例
| サービス名 | 主な内容 |
|---|---|
| 地域包括支援センター | 介護相談、専門員による支援と情報提供 |
| 介護予防教室 | 転倒防止体操・認知症予防プログラム |
| 家族会 | 相談・悩み共有・情報交換 |
このような支援を活用することで、自分に合った解決策や近隣のサポート情報も集めやすくなります。
介護保険外での補助策の検討
介護保険によるサービスだけでなく、自費で受けられる民間サービスや自治体独自の支援制度の利用も検討しましょう。例えば、食事の宅配や訪問介護・家事代行サービス、配食サービス、見守りシステムの導入など、家族の負担を軽減する取り組みが増えています。また、費用面が心配な方には福祉用具のレンタルや、住宅改修に使える各種補助金を検討するのも有効です。
介護保険外の主な活用例
| サービス | 概要 |
|---|---|
| 配食サービス | 栄養バランスを考慮した食事を自宅まで届ける |
| 家事代行 | 掃除や洗濯など日常生活のサポート |
| 見守りセンサー設置 | 遠方家族でも状態確認ができる |
| 住宅リフォーム補助金 | 手すり設置・段差解消などに適用 |
このような多様な補助策を組み合わせることで、老々介護の共倒れリスクや負担を大きく減らすことができます。
老々介護に関する最新情報と社会的動向
最新の統計データとトレンド解説
老々介護とは、高齢者同士が介護を担う状況を指し、現在の日本社会において深刻な課題となっています。最新の統計では、65歳以上の夫婦のみまたは高齢親子の世帯で、介護をしている割合が年々増加しており、直近の調査では全介護世帯の約4割近くが老々介護の状況に該当します。背景には高齢化社会の進展と平均寿命の延伸、核家族化が強く影響しています。
老々介護世帯の特徴として、介護する側も要介護認定を受けているケースが増加し、共倒れリスクの高まりが指摘されています。また、認知症を抱える高齢者同士の「認認介護」も増え、早期の社会的支援が重要となっています。
下記のポイントが注目されています。
-
老々介護世帯の増加傾向
-
介護者も高齢化・要介護化
-
認認介護の割合上昇
-
介護負担の長期化と精神的・経済的負担の深刻化
老々介護に関する社会問題・事件紹介
老々介護は家族を支え合う姿として美徳とされがちですが、実際には多くの問題点や事件が発生しています。最も深刻なのは、共倒れや孤立による悲劇的なケースです。
近年のニュースでも、80代の夫が同じく高齢の妻を介護しきれず事故や事件に至った例、認認介護で家庭内事故・介護疲れによる事件が複数報道されています。経済的な困窮や相談相手の不在、周囲の無理解も要因となっています。
主な課題は次の通りです。
-
共倒れ・介護うつのリスク増大
-
認知症同士の生活事故
-
介護費用・生活費の不足
-
社会的な支援や相談につながりにくい現状
介護のストレスや疲労から家庭内関係が悪化し、「親の介護で子供・娘が共倒れ」「母の介護で父との関係悪化」など家族全体の問題に発展するケースもあります。
参考になる書籍・資料・専門家情報
老々介護や認認介護への理解を深め、適切な対応策を知るためには、信頼できる情報源や専門家の意見を参考にすることが重要です。
書籍・資料の例
| 書籍・資料名 | 内容とポイント |
|---|---|
| 老老介護の現実と課題 | 老々介護の現状・データや課題を詳述 |
| 認知症介護ガイドブック | 認認介護への実践的アドバイス・事例あり |
| 厚生労働省「介護保険ガイド」 | 制度概要・利用方法・困ったときの相談先を解説 |
専門家・サポート窓口
-
地域包括支援センター
-
介護支援専門員(ケアマネジャー)
-
介護保険・福祉相談窓口
不安や困りごとがある場合には、早めに専門家へ相談することが高齢者本人と家族の負担軽減につながります。情報は日々アップデートされているため、最新の資料や専門家の意見も活用しましょう。
老々介護に関するよくある質問(Q&A)を包括的にまとめる
基礎知識に関する質問
老々介護とは、主に65歳以上の高齢者同士が介護を行う状況を指します。現代の日本社会において加齢による平均寿命の延伸とともに増加傾向にあり、夫婦や兄弟姉妹が介護者・被介護者の関係となるケースが目立ちます。
老々介護の現状と割合については、厚生労働省の調査によれば、全介護世帯のうち約30%以上が老々介護に該当し、今後も増加が予測されています。
以下の一覧で概要を確認できます。
| 用語 | 意味 | 備考 |
|---|---|---|
| 老々介護 | 高齢者が高齢者を介護する状況 | 夫婦・兄弟姉妹など |
| 認認介護 | 認知症の高齢者が認知症の高齢者を介護する状態 | 社会問題となっている |
| 老々介護 割合 | 介護世帯のうち老々介護が占める比率 | 約30%〜増加傾向 |
| 老々介護 英語 | Elderly care by the elderly(直訳) |
老々介護の読み方は「ろうろうかいご」です。
問題点や課題に関する質問
老々介護で特に大きな問題点は共倒れのリスクや経済的負担です。
体力や認知機能が低下している高齢者同士での介護は、事故や転倒、適切な医療・ケアが行き届かないケースを生みやすく、深刻な課題となっています。
主な問題点と課題は以下の通りです。
-
体力的・精神的負担の増大
介護する側も高齢であるため、長期間の介護は身体的な疲弊やストレスにつながります。 -
共倒れが社会問題に
「老々介護共倒れ」というキーワードで検索が増えるほど、介護者自身が倒れてしまうケースが増加しています。 -
経済的負担と生活費の不安
年金などの収入に限りがあり、介護サービスの利用料や医療費が家計を圧迫することも多いです。 -
家族や地域のサポート不足
子供世帯が遠方に住んでいたり、支援の輪が作りにくい現状があります。 -
認認介護の問題点
認知症患者同士の介護では、さらに安全対策や見守りの強化が必要です。
支援制度や具体的サービスに関する質問
老々介護の負担軽減には介護保険制度や地域包括支援センターの活用が役立ちます。各種サービスを適切に選び組み合わせることが重要です。
主な支援策やサービスは以下のようになります。
| 支援制度・サービス | 内容 | 利用方法 |
|---|---|---|
| 介護保険サービス | 訪問介護・デイサービス・ショートステイなど、多様な支援プラン | 市町村で申請 |
| 地域包括支援センター | 介護に関する総合相談・情報提供、ケアマネジャーの紹介 | 各自治体に相談 |
| 経済的支援(高額介護費など) | 一定額を超える介護費用の還付制度や、医療費控除 | 手続き必要 |
| 在宅介護サービス | 訪問看護や生活援助サービス、福祉用具のレンタルなど | ケアマネ経由 |
-
具体的に利用する際のポイント
- 市町村の窓口やケアマネジャーに相談し、状態や生活状況に最も合うサービスを組み合わせる
- 経済的負担が大きい場合は、高額介護サービス費制度や地域の助成制度も活用
高齢者自身だけで悩まず、周囲や専門家と相談しながら、最善の方法を見つけることが老々介護を乗り越える大切なポイントです。